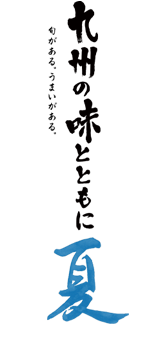
呉豆腐の味の決め手となるのは大豆。各店とも厳選した大豆から美味しい豆乳をつくることを心がけている
北海道産の馬鈴薯デンプン。葛を使わずデンプンだけを入れてじっくり練ることにより、こちらならではのトロトロ感ともちもち感を引き出す
かつては完全な手づくりだったが、今ではミキサーも導入されている。しかし、重要なポイントでの手作業は欠かせない

取材はご主人・前田淳一さんがつくった呉豆腐を食べるところから始まった。
「まずは呉豆腐を食べてみていただけますか?呉豆腐を味わっていただきたいのです」。
もちもちとしてやわらかい呉豆腐だけをいただくと、しっかりと大豆の味と香りがする。次にゴマがかなり細かくすられたゴマダレとすりショウガをかけて。香ばしいゴマの香りと醤油の風味が呉豆腐にからみつく。そして最後は黒蜜で。濃厚だがすっきりとした味わいの黒蜜がかかった呉豆腐は上品な甘味となる。“デザート”というよりも、和食会席の最後に出される “水菓子”という表現のほうがしっくりとくる。

「私は呉豆腐に、なめらかさ、弾力、大豆の香りと旨味を求めています。だから、佐賀県産のいい大豆、北海道十勝産馬鈴薯のいいでんぷん…いい素材を使ってます。温度や湿度をはじめ、毎日状態は変わるので、その時に合わせた材料の仕込み方やつくり方があります。よく、春夏秋冬と言いますが、日本にはもう一つ忘れてはならない、梅雨があります。大きく分けても、春、雨期、夏、秋、冬という5つのつくり方があることになりますね」。

前田さんが長年の経験から積み上げたつくり方の部分は撮影NGだ。
「中学生の頃は学校に行く前に毎朝呉豆腐を練りあげるのが日課でしたから、年季が入ってますね(笑)。当時は竈(くど)に鍋を置いて薪で火を焚いていましたね。私が長い時間の中で会得した呉豆腐をつくるための技は門外不出です。道具や機械も同じです。大豆を炊いて豆乳をつくる圧力釜も、電気設備も、呉豆腐を練る羽根の形状も、最善・最適を目指して少しずつ改良してきたものなんです。お見せできなくて申し訳ありません」。
できあがった呉豆腐を切るところだけは見せていただいた。

話を変えて、先ほどいただいたゴマダレと黒蜜についてうかがった。
「ゴマを煎る機械も改良してますね。ゴマダレは、ゴマと醤油以外に、あるものも入れています。それからまろやかさを出すためにねかせるので完成までに6〜7カ月はかかります。黒蜜は、純国産の天然蜂蜜と沖縄産黒糖、きび糖からつくります。蜂蜜は福岡の養蜂農家のものでアカシアやレンゲなどの蜜を使っています。数えきれない失敗の中からついに開発した作り方と味です。こちらも完成までに2〜3カ月かかりますね。私は酒も好きだけど甘いものも好き。呉豆腐に黒蜜をかけたものは、黒霧島にとても合いますよ(笑)」。
呉豆腐を美味しく食べるためのゴマタレや黒蜜に関しても、この力の入れよう。呉豆腐をどれだけ丹念につくっているのかが容易に想像できるというものだ。

呉豆腐づくりにおいて、一番難しい作業は工程の最後にやってくるという前田さん。そのためもあってか、仕事をする上で常に“余裕”が大切なのだという。
「自分の体力が100あるとしたら、その15くらいを使って仕事をすることが大事だと思います。余裕がないといけません。あまりにも突き詰めると、行き詰まっていやになってしまいますし。難しく考えながらやったとしてもできあがるものは同じですから。集中すべきところに力を込められる準備が必要です。それから、余裕を持ってやっていると、『仕事しようかな』という前向きな気持ちにも自然になりますからね(笑)」。
「時間が経ってかたくなってしまった呉豆腐は、水を切って、ラップをせずにレンジにでチンして水で冷やすと、また美味しく食べられますよ」と教えてくれた前田さん。常に呉豆腐の研究に余念はない。
「有田の方言で“呉”は練るという意味もあるんですよ。『あの人は呉の強か』という言い方もあって、それは『あの人は粘り強い人』という意味です」。
呉豆腐に関しては、前田さんは『呉の強か人』に間違いなさそうだ。

呉豆腐に大豆の香りとうまみを求めている前田さん。それを達成させるために使っている大豆は、佐賀県産の大豆だ

なめらかさと弾力も、前田さんが呉豆腐に求めているもの。北海道十勝産馬鈴薯からつくられるデンプンを使うことも重要なポイント

温度や湿度をはじめ、日々変わる状態に合わせた材料の仕込み方やつくり方を行なっている。工房には工夫を凝らしたシステムも設置している
中学生の頃から家業の手伝いで呉豆腐を練っていたという店主・前田淳一さん。その経験をベースに、呉豆腐づくりに様々な工夫を凝らしている。佐賀県産大豆と北海道十勝産馬鈴薯のデンプンを使った呉豆腐は、つるんとしてもちもちした食感の中に、大豆の甘味を感じられる。それをさらに美味しく食べるためのゴマダレと黒蜜も自家製だ。



