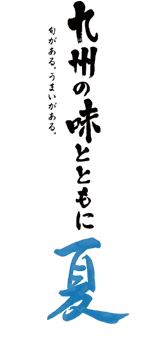
アジ、イリコ、カマスがよく使われるが、タイなどを使うことも。焼いてほぐしたあと、味噌と一緒にすり鉢で練る
焼き味噌(冷汁の素)を溶く出汁は昆布、カツオ出汁ベースにする場合が多いが、焼き味噌によっては冷水で溶く場合もある
冷汁に入る具材や薬味としては、キュウリ、豆腐、大葉がよく用いられる。地域ごと、作り手ごとにアレンジが加わることも多い

都城生まれの塚野さんは、16歳の時から料理の仕事を始めた。
「割烹に丁稚に行っていた時、まかないで出ていた冷汁は修行時代の思い出の味ですね。初めて食べた時、こんなにおいしいものがあるのかと思いました。お店の方が作ってくれて仲居さんたちとみんなで食べていました。今、私が作っている冷汁もその時の味がベースですね」。

さて、その味とは…
さばいたアジをまるごと焼いて身をほぐした後、骨まで使う。通常は使わない骨まで使うのが“つか野流”だ。
「骨だけをこんがり焼いて使うんです」。

すり鉢にその骨を入れてすりこぎで丹念にすりつぶす。ゴリゴリという音がだんだん小さくなり骨は粉末状に。そこにアジの身と都城産の麦味噌を入れてすりつぶす。

具材として冷汁に浮かべる豆腐を、この段階で入れて一緒にすりつぶすのも“つか野流”。
「それが、私が作ってもらい、食べていたやり方なんです」。

身も骨もまるごと一匹のアジ、麦味噌、豆腐が全体になじんでペースト状になったら、すり鉢の内側にうすく伸ばしていく。フォカッチャのように指で表面に穴をあけ、すり鉢をさかさにしてガスの上に置き焼いていく。
「香ばしい香りにするための仕上げです。弱火でじっくり焼きあげます。表面がきつね色になったらできあがりですが、漂ってくる香りで判断できますね」。
焼き上がったら、それを適当な大きさにまるめて“味噌玉”を作っておく。
お客さんからの注文が入ると、すり鉢に白ごまを少し入れてすり、みそ玉を入れる。冷水を少しずつ入れながら溶いていく。
「味噌玉にはしっかり味がついているので、味がくどくならないように私は冷水を使います」。
上にのせる具材はきゅうり、大葉、ミョウガ。シャキシャキ感を出すためにキュウリは水でさらしておくが、濃い風味が残るように大葉は最後に切る。だから、大葉を包丁で切るトントントンという音がしてきたらもうすぐできあがりのサインだ。
具材をすべて入れ、最後に白ごまと氷を浮かべて完成。山椒の木でできたすりこぎもすり鉢に入れて出す。
「風情が出ますから(笑)」。

塚野さんの冷汁のもう一つの特徴。普通の冷汁は熱々のごはんなのだが冷たいごはんを使うこと。しかし、“冷えたごはん”ではない。注文が入ってから、熱いごはんを入れたボウルを氷水にあてて冷やすのだ。
「どばっとかけてかきこんでください」。
喉越しの冷たい冷汁とごはんは、まさに夏に食がすすむ一品。その味わいには、できあがりを見ただけではわからない手間と技がつまっている。
「カウンターに座るお客さんからは、いつも仕事しているところを見られているので背中に汗かきながらやってます(笑)。けれど料理の仕事は楽しいですよ」。
塚野さんはいつも「食を通して地元に貢献したい」と考えているのだという。しっかりと朝ごはんも食べてもらいたいと思い、朝は朝食としてお粥も提供しているのだ。そんな塚野さんの想いは訪れる方々にしっかりと伝わり、素敵な関係も生まれているようだ。
「先ほど食べていただいた冷汁の大葉は、朝粥を食べにきてくださったお客さんが差し入れてくださったものなんですよ」。

アジを焼いて身をほぐすが、骨も焼いて丸ごと一匹のアジを使う。まず骨をすりつぶして粉状にした後、麦味噌と身を入れてさらにすりつぶす

魚、味噌、豆腐をすりつぶして焼いたものにしっかりと味がついているので、出汁ではなく冷水で溶く。少しずつ水を加えながら丹念に溶いていく

きゅうり、ミョウガ、風味を残すため最後に切る大葉が具材。豆腐はちぎって入れるのではなく、魚や味噌などと一緒にすりつぶしている
粗塩と醤油のくずあんがつく朝がゆ(735円)、冷汁定食(840円)、おにぎり点心(1050円)他の昼食、夜は飲み処(コース料理4200円〜)と様々な食を楽しめる。朝から夜まで一人で料理を作るのは、都城出身の店主・塚野次利さん。「食を通して地元に貢献したい」と、都城の方々のために身体にやさしい味を提供している。


