

独特の甘味と風味を持つ地酒が旨味を醸す
江戸時代から続く華やかな料理
『酒ずし』の始まりは400年も続く伝統華麗なもの。島津の殿様が開いた花見弁当。宴会などの残ったごはんにお酒を桶に入れておいたところ、翌朝発酵して良い香りが漂う美味しい料理になっていたと言われている。また、かつて男性の立場が強かった鹿児島で、女性が花見の時に酒を楽しむために『酒ずし』を考えだしたという説もある。やがて、琉球塗りの桶を使った豪華な料理として広まり、今に伝わる。使われる酒は清酒ではなく、『灰持酒(あくもちしゅ)』で、鹿児島では「地酒」と呼ばれている。
桶の中に地酒をまぶしたごはんを広げ、その上にそれぞれに下ごしらえして味付けしたタケノコ・ツワやフキ・シイタケ・卵焼き・さつま揚げなどの具材を広げる。それを繰り返して2~3層をつくり、最後にタイ・エビ・木の芽(山椒の若葉)などをのせ、地酒をふりかけてふたをする。おもしをのせ、5~6時間寝かせて発酵がすすむとできあがり。伝統的な作り方では、一升のごはんに対して一升の地酒を使う。“すし”とは言っても、ごはんに酢や砂糖を合わせてすし飯を作るわけではないことも特徴だ。地酒の独特の甘味と風味、具材の旨味が重なり合い、しっとりとしたごはん一粒ずつにもその味わいが染み込んでいる。
作り手によって中に入る具材は異なるが、『酒ずし』は春に生まれた料理であると言われているだけに、春に旬を迎えるタケノコやフキなどがよく使われている。
鹿児島女子短期大学名誉教授・福司山エツ子先生を訪ね、酒ずしの始まり、栄養、食文化的側面など様々な側面から見た『酒ずし』のお話をうかがった。
福司山先生の専門は“栄養・調理”で、お茶やさつまいもの特性を活かした料理、鹿児島の食材と料理等を研究されてきた。郷伝会(きょうでんかい・今に活かす鹿児島女子短期大学名誉教授・福司山エツ子先生を訪ね、様々な側面から見た『酒ずし』のお話をうかがった。
●『酒ずし』の旨さの秘密
「地酒はアミノ酸が豊富で豊かな旨味と上品な甘味を持っています。この旨味そのものに発酵の力が加わることで、『酒ずし』独特の味わいを醸し出すのです。デンプンが糖化することで消化にもよいので、私は高齢者の方には「食べる点滴」としてすすめています。
●『酒ずし』を作る桶
「独特の形については、鹿児島を舞台に描いた小説『南の風』の一節で、『馬盥(うまだらい)によく似た…』という表現があります。琉球塗りで飴色の胴体に竹のタガ…桶はさつま武士を感じさせる横綱の貫禄。
●『酒ずし』の起源
「島津の殿様が宴を開き、そこで余ったごちそうを残った酒と一緒に桶に入れておいたら、翌朝、発酵して美味しい料理になったと言われています。余ったものを捨てずにとっておいたという、“もったいない”から生まれた料理でもあったのだと思います」。
●『酒ずし』と春の食材
「『酒ずし』にはタケノコ、フキ、桜ダイなど春に旬を迎える海の幸、山の幸がよく使われます。春のタケノコは水煮とは違い瑞々しいですし、フキの香りも春は格別です。桶の中に旬の海の幸、山の幸を重ねていくのですから、素朴なものが多い鹿児島の郷土料理の中で、一際豪華な料理ですね。」
●『酒ずし』と合わせる料理
「青のりと豆腐のすまし汁などをよく合わせますね。青のりの緑色と豆腐の白色は、華やかな色合いの『酒ずし』ともよく合います」。
●『酒ずし』を美味しく作るコツ
「旬の食材を使うこと、それぞれに下味をつけておくことなども必要ですが、地酒をたっぷりと使い、じっくりとねかせて発酵させることが必要です。時間が美味しくしてくれる料理なのです。ごはんは40度、具材は30度になってから作り始めるなど、発酵がうまく進むように、ごはんと具材の温度にも気を配るとよいですね」。
鹿児島でつくられる灰持酒(あくもちしゅ)を鹿児島では『地酒』と呼んでいる。灰持酒とは、途中までは清酒づくりと同じ工程であるが、もろみに灰を加えてから絞る清酒の一種で、赤褐色で独特の甘味と風味を持つ。
温暖な鹿児島では清酒造りが難しいことから、保存性を高めるためにこの造り方が行なわれていた。かつては祝いの席などで飲まれることもあったが、現在は『酒ずし』をはじめ、料理酒として使われることがほとんど。灰がアルカリ性であることから、煮物に使うと肉や魚の身をやわらかくする。
![]()
シイタケ、タケノコ、フキ、カマボコ、卵焼き、タイ、エビ、キビナゴ、木の芽などが使われる。春に旬を迎える食材が中心だ
“すし”とは言っても酢は使わず、ごはんと合わせるのは地酒。具材はそれぞれ別々に下味がつけられている
『酒ずし』用の桶に、ごはんと具材を交互に広げ、層を重ねる。地酒をたっぷりと注いでふたをし、おもしをして一晩ねかせる
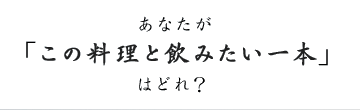
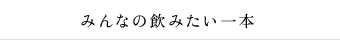



3本の中から飲みたい一本をお選びください。
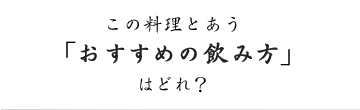
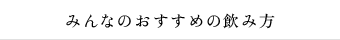



3種類の飲み方からおすすめを一つお選びください。
