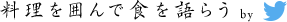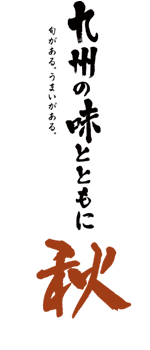

ポルトガル人宣教師の勧めから生まれた
素朴で甘辛い豚肉と野菜の炒めもの
『浦上(うらかみ)そぼろ』は、名前に“そぼろ”とあるが、挽肉が入っているわけではない。細切りにされた豚肉や野菜を甘辛く炒めた、野菜炒めにもキンピラにも似た味わい。長崎市浦上地区を中心に伝わる郷土料理だ。
日本にキリスト教が伝わった後、浦上地区でも布教活動が行なわれ、カトリック信者が多い街となった。滞在するポルトガル人宣教師が、健康に良いと日本人に豚肉を食べることを勧めたことが、豚肉を使う『浦上そぼろ』が生まれたきっかけとなったという。名前の由来は、ポルトガル語で“余り物”を意味する“ソブラード”からきたという説も、素材を粗く切ることを表す“粗ぼろ(そぼろ)”からきたという説もある。
欠かせない素材は豚肉、ゴボウ、モヤシ。その他に人参、コンニャクなどを入れることも多い。家庭で食べられてきた料理ゆえ、様々な残り物が加わることもある。すべてを同じくらいの大きさの細切りにして炒め、味付けしていく。味付けには出汁、酒、醤油などを使い、炒め煮するような感覚。そこが普通の炒め物とは違うところだ。長崎だけに、調味料には、砂糖も欠かせない。また、モヤシはシャキシャキの歯応えを残すため、最後に鍋の中に入れられる。
素朴で飽きない味わいは、ごはんのおかずとしても、焼酎の肴としても最高のもの。長崎では学校給食としても食べられ、すべての世代に愛されている。
1549年、日本にキリスト教伝来。長崎にも、キリスト教が伝えられた1567年頃から、浦上でも布教が行なわれはじめ、やがてカトリック信者の多い街となっていった。
しかし、1587年豊臣秀吉による宣教師追放令、そして1612年徳川家康による禁教令が発布。続いて、1637年の島原の乱の影響から、1639年にはポルトガル船の日本渡航禁止とポルトガル人の国外追放が命じられた。それ以降、日本の国外との貿易は唐船貿易のみとなり、ポルトガルの文化にふれることはなくなってしまった。
ポルトガル人宣教師の影響で生まれた『浦上そぼろ』は、1500年代後半から食べられていると推測される。
![]()
豚肉、ゴボウ、モヤシ以外は、何を使ってもかまわない。彩りや季節を考えて、作り手が工夫する。家庭では残り物が使われることも
醤油、酒、ミリンなどとともに出汁を使うことが特徴。甘味をつけるため砂糖が多めに入るのも長崎ならではだ
細切りにした具材を炒め、調味料を入れて炒め煮する。モヤシは歯応えを残すために最後に入れる
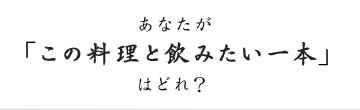
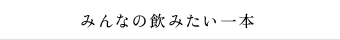



3本の中から飲みたい一本をお選びください。
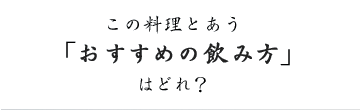
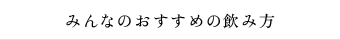



3種類の飲み方からおすすめを一つお選びください。