一升瓶の品質を守る検査員たち。
その一瞬の判断が、品質を支えている。
「もったいない」という言葉に代表されるように、日本では古くから、日用品を使い捨てることなく、再利用する文化が根付いている。江戸時代には紙くずや着物の回収業者が存在していたほか、金属製品や漆器を修理する職人も数多く存在していたという。
明治時代のはじめごろ、各種洋酒の輸入が始まりガラス瓶が日本に上陸すると、使用済みの瓶を買い集めて販売する商売が生まれる。このリユース文化は1901年に国内でガラス瓶の生産が始まり、一升瓶と呼ばれる1800ml瓶に入った清酒が登場したことでさらに広まっていった。これが後に「リターナブルびん」と呼ばれるようになる“再利用される瓶”の原型である。

リターナブルびんとは、使用後、回収・洗浄され、ガラス瓶のまま再び商品として再利用される瓶のことであり、日本では100年以上前から使用されていると言われている。
「環境への影響に配慮した前社長の方針で、霧島酒造の一升瓶ラインでは現在もリターナブルびんを使用しています※」
そう教えてくれたのは、ボトリング部の山下満裕だ。
当時、全国的にリユース率が高かったとされる一升瓶。そのような背景もあり、霧島酒造でもリターナブルびんの使用が始まった。
焼酎を瓶やパックに詰める工程は、ボトリング部が担っており、容器の種類によってラインを分けて作業しているが、そのなかでも一升瓶のラインは少し特殊である。
※吉助などの一部商品を除く
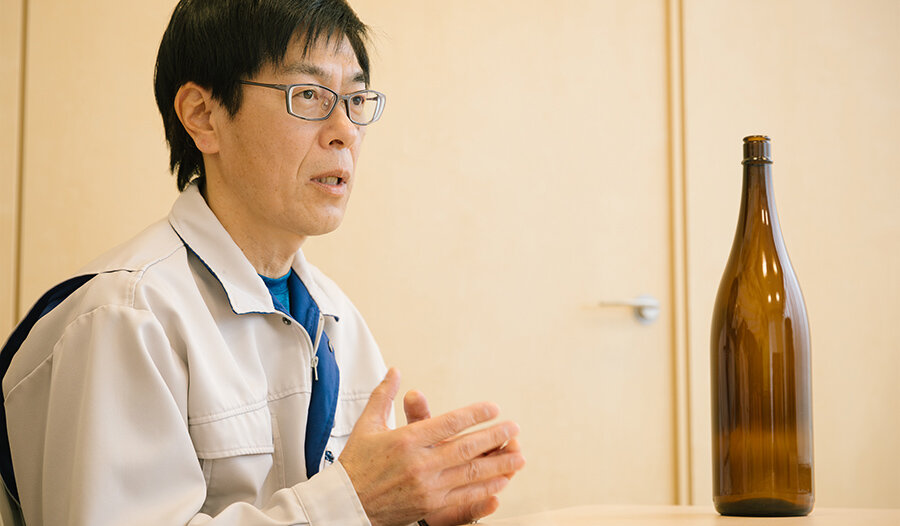
リターナブルびんを使うということは、ボトリング工程での洗浄や検査などが、通常の容器以上に必要になるということ。洗浄後は、瓶に傷や欠けがないかの徹底したチェックを行う。その検査は、ラインに設置された空瓶検査機1台と、検査員3名による目視検査という厳重な体制で行われている。
3名の検査員は、それぞれ口部分、胴部分、底部分で担当を分けて、バックライトの前を流れてくる瓶に目を光らせている。1分間に約160本。その速さで流れてくる瓶を、瞬時にチェックしなければならない。

「瞬きもできないほど集中する必要があるので、目を労るための目薬は必需品ですね」
そう語る末原莉子も、検査員のひとりだ。
検査員は、ボトリング部のなかでも、訓練を受けテストに合格した人しか務めることができない特別な役割。一人前の検査員になるまでには、半年から一年ほどの訓練が必要であり、多数いるボトリング部の中でも、一升瓶のラインで検査員として認定された社員は15人※ほどしかいない。
※2024年5月時点

「人間の集中力は、20~30分が限界と言われているので、20分交代で作業を行っています」
求められる集中力と忍耐力は、アスリートのようだ。実際に、傷の入った瓶のサンプルをいくつか見せてもらったが、素人目には判別が難しいものもあった。検査員ではない山下も「私でも『どこに!?』と気づかないことがあります」と苦笑い。そんな微かな傷を、検査員たちは瞬時に見つけているのだ。
末原は語る。
「瓶に手や口が触れる可能性がある以上、私たちは様々な想定をした上で、お客様に安全を保証する必要があります。それは、製造の方たちが焼酎の品質にかける想いと、なにも変わりません」

なぜ検査機を増やさないのかと、素朴な疑問を投げかけた。
「機械は、傷があるかないかの“判定”はできても、それがOKかNGかの“判断”はできないからです」と山下は答える。
一度は市場に出回った瓶だ。多少の傷は必ずある。その傷を「破損につながるかどうか」「商品として外観上問題があるかどうか」などの視点で判断をすることが、リターナブルびんを使用する上で重要なことであり、それは現状、機械には難しいことなのだ。
「AIやカメラの性能が進化している昨今、検査体制をいかにより良くしていけるかが今後の私たちの課題だと感じています」

焼酎造りは自然の恵みがあってこそできるもの。
だからこそ、環境負荷の少ない焼酎造りのスタイルを常に模索し続けていく必要がある。時代と共にその手法が変わったとしても、お客様がおいしい焼酎を安心して楽しめるようにという考え方は、これからも変わることはない。
検査員の人の目による厳しい検査体制が、霧島酒造の品質を支えている。

※20歳未満の方へのお酒に関する情報の共有はお控えください。


